昼から東京都写真美術館へ。恵比寿映像祭にいく。

恵比寿映像祭 2026 Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions 2026
恵比寿映像祭は約2週間にわたり、展示、上映、ライヴ・パフォーマンス、関連イヴェントなどによって複合的に構成する、映像とアートの国際フェスティヴァルです。
美術館で映像を見たことはあまりなかったので、どれも新鮮な体験で面白かった。映像が実験的であるということは、その動画を映し出すメディアに対して意識的な作品を作るということで、それはつまり自宅でスマホの画面を通して作品を鑑賞するのとはまったく異なる体験を提供してくれるということだ。
たとえば台湾の作家、劉玗(リウ・ユー)の「If Narratives Become the Great Flood」という作品では、スクリーンの前に設置された動物を模したオブジェクトに映像が投射され、物質的な重みとしてその背後に見える映像と共鳴する。それはときに画面を隠す影にもなって、空間的な広がりを否応なく見せてくれる。

角田俊也のキュレーションは、ベニヤ板やら釘やらを貼り付けた壁に、海の中で撮られた光の映像を重ね合わせる作品。映像というものが、単に光源から送り込まれる光だけでなく、それを反射する支持体との相互作用によって生み出されるものであることを改めて実感させてくれる。
まあどれも、正直なところ家でゴロゴロしながら見ることはできない作品ばかりであった。これは悪い意味ではなくて、ある意味では「退屈な」作品が、美術館という場所に置かれることで「退屈しない」作品に変わるということが面白かった。映像が意味するナラティブは後景に引き、とにかく意味を欠いた純粋な「記録」が強調されている。
帰り道に、一枚写真を撮った。

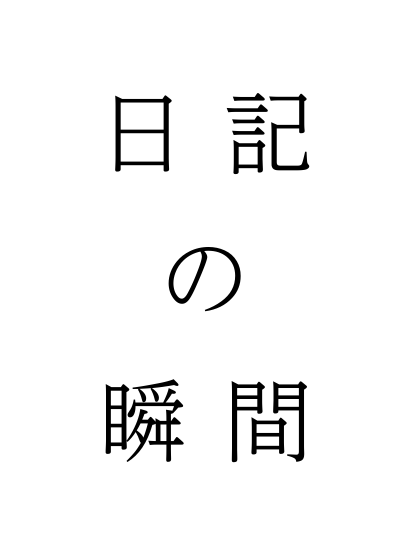


コメント