ENBU中間制作の上映会。同期の作品と自分の作品を一日通して見るわけだが、これがまあ、なんとも自分の力不足というか至らなさを突きつけられるような時間で、楽しかった反面、かなり苦しかった。
まずわかりやすい反省としては、音合わせに失敗していたということ。家のモニターで見ていた時は違和感なかった気がしていたのに、ちょっと見ていられないくらいに音ズレがあった。「ピンマイクの音はフレームを変えなきゃいけない」という基礎的なところがわかっていなかったのが原因だが、これでOKを出して上映してしまった自分のマインドが良くないと思った。ちゃんと上映前に時間をとって人に見てもらえばこんなことは起こらなかったはず。ひとまずは諸先輩方の教えを請うて、ベストな音を作って完成としたい。
これに紐づく話だけれど、やっぱりピンマイクって渋いのかもしれない。なるべくガンマイクの音を使えるように、録音から整音まできっちりとやっていく必要がある。ただ「整音」ってどんなプロセスなんだ……? とにかく、音をきっちり仕上げる方法を近々で学ばなければならない。
で、次は脚本・演出の反省。まず第一に、話がかなりのっぺりしていたと思う。「わかりやすい」みたいなことを言ってはくれたけれど、しかしまあ、見せどころというか、全体から見てはみ出ている場面を作れなかったのは大きな失敗だったと思う。もうちょっとちゃんと言葉にしたいな。うーん。全てのシーンが物語に奉仕してしまったというか。異質なところ・記憶に残る場面を作れなかった。これはかなりの程度脚本でコントロールできる部分だとも思うが、現場の思いつきみたいなレベルでも、まだまだ思慮が浅かったと思う。つまりは『ソナチネ』の「人間紙相撲」のような場面がない。それをやるのがフィクションの醍醐味だろうに、完成させることに意識を持って行きすぎたのかもしれない。「アイデアを出さなければダメだ」という危機意識が足りなかった。アイデアがなければ映画は面白くならない。
会話が難しい。ちょっと笑ってもらえるようなダイアローグを書いたつもりだったが、全然ダメ。「軽さ」というか、会話のグルーブ感みたいなものが作れなかった。これはシナリオのレベルでも、演出のレベルでもある問題だと思うが、どうしたらいいのかまだよくわかっていない。面白い言葉を書くのは当然として、しかしそれだけでなく、その空気感・温度感みたいなものを、間とか声のトーンで作る必要がある。これは脚本・演出・編集にわたるかなり難しいテーマだとは思うな。色々と仮説立てながら、短い会話劇をたくさん作っていく。
あと、役者さんを上手く動かせなかったことも反省。特に長めの会話シーンだと、画面内で人や背景がもっと動く必要があると思った。だから乗り物って会話シーンに向いているのだと思うが、そもそも僕が現場で役者さんの身振りまで観察できていたかというと、ほとんどできていないというのが正直なところ。
でかい問題として、いわゆる「自然な」言葉っていうものを書いたり演出しようとしても、結局はリアルに勝てないということを痛感した。稚拙な「言いそうなこと」を言ってもらうくらいなら「言いそうもないこと」を言ってもらうことでしかフィクションを作る意味はないのではないか、と。というのも、同期の一人が作ったもの、中国の風景ととある家の日常を映した映画があったのだが、これがまあすごく胸に刺さるというか、魅力的な画面ばかりだった。編集はかなり上手い(その上手さはなかなか言葉にし難い)のだが、それだけでなく、あらゆる身振りが自然だし、しっかりと「人生」を背負っているような感覚がある。ちゃんと人と向き合って、正しい位置にカメラを置けば映画になるということをまざまざと突きつけられて、ただそれでもなお「フィクション」の枠組みの中に留まる方法はないのだろうかと、自分のやっていることの基盤を揺さぶられてしまった。
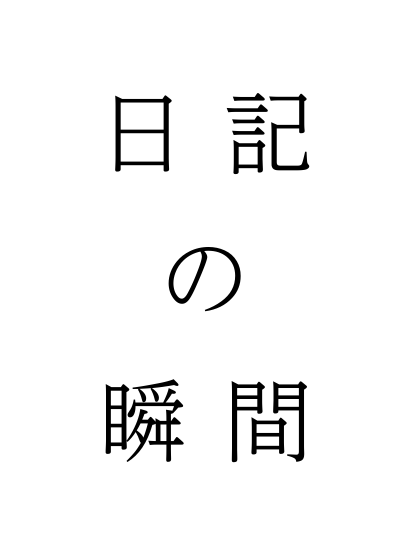


コメント