真夜中のギター。シャッターを閉めたそうにする改札。人肌のコンクリート。サラリーマンのハレとケを失って久しい僕は、汗臭いスーツ姿とともに詰め込まれるほろ酔いの終電にノスタルジーを感じて始めている。同じ場所でも、違う場所。ここはもう僕の居場所ではないらしい。
思えば僕は労働をこよなく愛していた。憎たらしい取引先の後ろ姿に中指を立てて、精一杯のウィットを込めた愚痴をハイボールとともに東心斎橋の排水溝に垂れ流す日々を愛していた。ジンジンと音を立てる脳みそをひっさげて、透明の空の下、シマトネリコの並木道を朝日とともに散歩する時間を愛していた。無職。ニート。フリーランス。個人事業主。どの衣装に袖を通してもサイズが合わないのはそのせいである。
出版社を立ち上げたら、なぜかわからないが講演するように頼まれた。いまはその帰りである。講演はややウケであった。どうやら僕は安居酒屋で悪口の品評会をして座布団を送りあうくらいが性に合っているらしい。講演中、すやすやと寝息を立てていた女性は、酒というガソリンを注いだ途端に爆音を吹かせている。なんだ、イケるクチじゃないか。
人生100年時代らしい。僕は32歳。つまり、死ぬまで68年。ノスタルジーの種に水をやり、花を咲かせる時間はまだあるだろうか? それともデジタルリマスターされていく記憶をお気に入り登録して死ぬまで繰り返すのだろうか?
どうやら僕はいま弱音を吐いているらしい。その意味を知っているのは僕だけである。それでも僕は弱音にリボンをかけて、誰かに届けたかった。僕はプレゼントを贈るチャンスをプレゼントされた。そして僕がプレゼントを贈り、プレゼントを贈るチャンスもプレゼントする。そうすることでようやく自分のもとに届く。誰にも出さない手紙は、自分のもとにも届かない。
でも、言葉はいつだって輪郭をなぞるだけ。核心を抉り取る前に、恐る恐る道具箱に帰っていく。それでも僕は、言葉という手垢の染みついた道具を握りしめて、またあしたの弱音にリボンをかける。
あのままシャッターに締め出されることもできた。でも僕は帰る。あの居場所は、あの場所に置いてきたのだから。

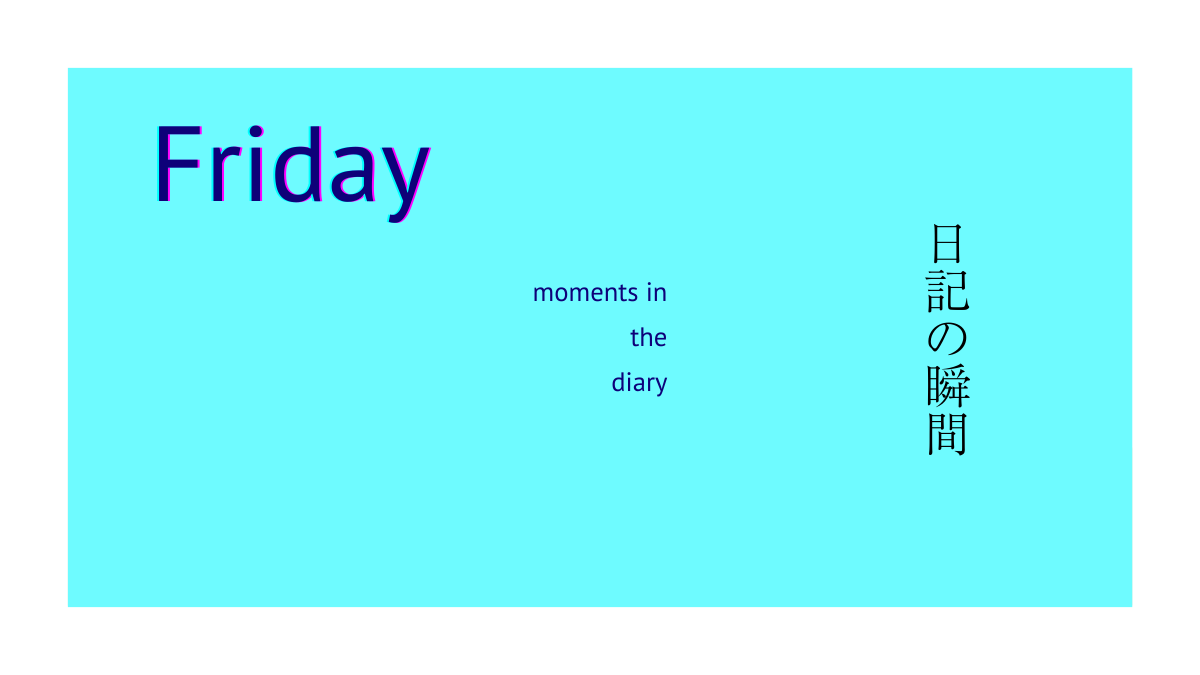

コメント