最寄り駅のホームに、くたびれたスヌーピーのぬいぐるみが放置されていた。
大して忙しいわけではなかったのに、なんやかんやでぐったりと疲れた身体を引きずって電車を降りると、改札へと繋がる階段の近くで、だらりと手足を投げ出したスヌーピーの姿を見る。白かった肌は少し黒ずんで、しぼんだようにハリがない。疲れた目は焦点が合っていないようにも見える。
一度立ち止まり、そのぬいぐるみをじっと見つめる。誰かの落とし物なのだろうが、いささか何かの象徴めいた雰囲気が漂っていると思う。が、人の波を背後に感じて、すぐにその場を立ち去る。明日の朝にまた会えるかしら、と少しばかりの期待を込めて、帰路に着く。
近くのコンビニで、文芸ブルータスを買う。ざっと紙面を流し読みし、市川沙央と村上春樹の短編を読む。村上春樹の小説——『夏帆』という去年『新潮』に掲載されたものの改訂版らしい——は、次のように始まる。
「これまでいろんな女性とデートのようなことをしてきたが」とその男は言った。「正直いって、君みたいに醜い相手は初めてだよ」
ちょうど今、「場が凍りつく」瞬間を描いたシナリオを書いていたから、何か親和性のようなものを感じる。が、やっぱり短編として上手いなあ、と思うのは、その瞬間がちゃんと冒頭に出てくるというところ。で、ヒヤッとした空気を作った後に、主人公は誰で、相手はどんな人間で、どんなシチュエーションでその言葉が発せられたのかを説明していく。
これって映像でできるのかしら。フラッシュフォワードで過去を描き、中盤くらいで冒頭の現在に戻る。で、後半でその後の展開に進む構成になるのだろうが、でもそれって映画としては退屈じゃない?とも思う。回想は使わずに「とにかく現在時で突っ走れ」というのが今の僕の指針になっていて、それを悪い方針だとは思っていないが、ただそうすると冒頭は来たる中盤の「場が凍りつく」瞬間の段取りのようにもなってしまって、キレがなくなってしまうという問題もあるだろう。
よくよく思い返してみると、村上春樹の短編ってどれも【現在→過去→未来】の構成になっていたような気もする。おそらくはそれが短い小説を短いままに分厚くする戦略なのだろう(意識的か無意識のうちかは置いておくことにして)。そしてそれは「一場面から過去と未来を開く」ための有用なやり方でもあるのだろう。
とはいえ、やっぱり映画でその構成を取るのはあまり好きではないな、と思い直す。結局は延々と「現在」を垂れ流しつつ、その現在の後ろに過去ないし未来を仄めかすことができるように、映っている時間の密度を上げることだけを考えていけば良いはず、と自分に言い聞かせる。
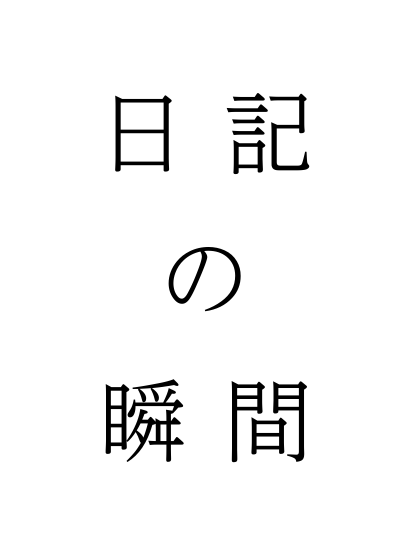


コメント