ENBUの授業で、三宅唱の作品や『SUPER HAPPY FOREVER』の編集を担当している大川景子さんの話を聞く。学生映画のワンシーンを見ながら、他に編集の可能性がないかを皆で探っていく。
ショットとショットが切り替わるタイミングを「編集点」と呼んだりするのだが、印象深かったのは、アクションつなぎ(人物の動作に合わせて編集する)は少し安易なのではないか、ということ。もちろんその繋ぎが悪いわけではないが、たとえば座る動きのタイミングで画面が切り替わると、否応なくその動作が強調されてしまう。「自然な繋がり」という意味ではそう繋ぎたくなる意味もわかるが、作品のトーンやそのシーンの役割を考えた際に、そこで生まれるスピード感が全体と噛み合わなくなってしまう場合もある。
続いて、大川さん自身が編集した作品の素材と粗編集、完成版の三パターンを見ていく。「どのショットも魅力がある」と話してもらったのが心に残った。悪い部分を編集で誤魔化していくのではなく、多様な魅力にあふれた各ショットから、そのシーンで必要なものを絞り込んでいくのが編集の作業であるということ。その話を聞いてから実際に会話シーンのショットを見ていくと、それぞれのクロースアップには相手の言葉に対するリアクションが繊細な表情の変化として映っているし、向き合う二人をひとつの画面に写したショットには、両者の対比が姿勢やら動き・背景のビジュアルで明確になっている。たしかにどれも魅力的で、「これってどうしたらいいの?」とかなり困ってしまう。
おそらくは、ポジティブな意味で「もう編集なんてできないよ」と思えるくらいに全てのショットに魅力を見出していくことが最も重要なのだろうと思った。単に「このショットの次はこのショット」と機械的に選択するのではなく、まずは個々の魅力を改めて凝視すること。そして、それら複数の魅力の中から、映画全体の中で何が必要なのかを考えていくこと。
また、個人的に勇気づけられたのは、大川さんも編集を始めてから一ヶ月くらいは全く見通しが立たないと言っていたことだった。とにかくガチャガチャと手を動かしながら素材を見ていくことで、要約一つひとつののカットが頭に入ってくる。それでようやく「監督と対等に話せるようになる」と言っていたのが印象的だった。
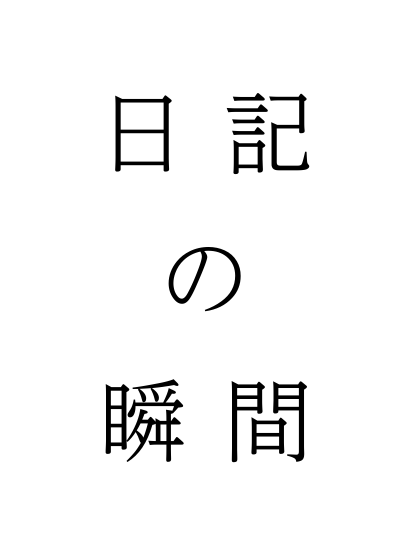

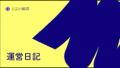

コメント